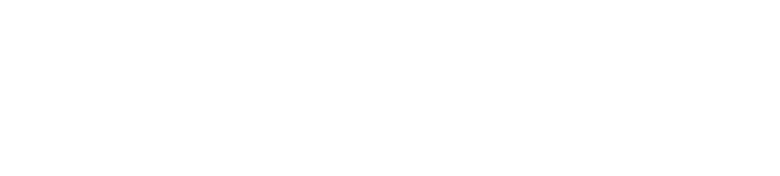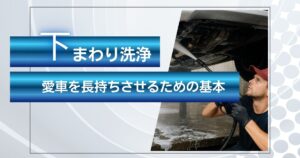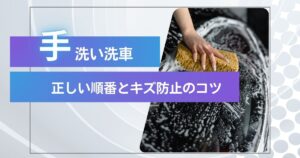車のサビは、一度発生すると静かに広がり、放置すれば塗装の剥がれや穴あき、最悪の場合は車検不合格につながることもあります。特に雪国や海沿いなど、湿気や塩分が多い環境ではサビの進行が早く、早期発見と対策が欠かせません。
本記事では、サビの原因からDIYでできる除去手順、プロ施工との違い、そして再発を防ぐための予防策まで、プロの視点でわかりやすく解説します。愛車を長く、美しく保つために、ぜひ最後までご覧ください。
車のサビとは?発生原因と種類

愛車の見た目を損なうだけでなく、放置すると強度低下や車検不合格の原因にもなる「サビ」。特に雪国や海沿いなどの過酷な環境では進行が早く、早期発見と適切な対処が重要です。ここでは、サビができるメカニズムや種類、発生しやすい場所を解説します。
サビが発生するメカニズム
車の金属部分は、酸素と水分が反応する「酸化反応」によってサビが発生します。これに塩分(融雪剤や海水中の塩)が加わると化学反応が加速し、サビの進行スピードが一気に上がります。
また、走行中の飛び石や擦り傷で塗装が剥がれると、その部分から金属が露出し、サビの「入り口」となります。
主なサビの発生要因
- 水分(雨・湿気・洗車後の拭き残し)
- 塩分(融雪剤・海水)
- 傷や飛び石による塗装の剥がれ
- 長期間の汚れ放置
サビの種類(表面サビ/進行サビ/穴あき)
サビには進行度に応じて段階があります。適切な対処方法は、この種類によって異なります。
- 表面サビ
塗装表面やごく浅い部分にできるサビ。茶色やオレンジ色の変色が見られます。早期であれば研磨やケミカルで除去可能。 - 進行サビ
サビが塗装下や金属内部まで広がった状態。表面は膨らみや剥がれがあり、内部まで腐食が進んでいます。部分補修やパネル交換が必要なことも。 - 穴あき(貫通サビ)
腐食が金属を貫通し、穴があいた状態。構造的な強度が低下しており、部品交換や溶接修理が必要です。
発生しやすい場所
車のサビは、以下のように水分や塩分が溜まりやすい・傷つきやすい部分に集中します。
- 下回り(シャーシ、フレーム):融雪剤や泥水が直接付着
- ホイールハウス(タイヤハウス):飛び石・泥はねで塗装剥がれやすい
- ドア下(サイドシル):雨水や泥が溜まりやすい
- ボディパネルの端部や溶接部:塗装が薄くなりやすい部分
- トランクやボンネットの縁:ゴムパッキン周りに水が残りやすい
こうした場所を意識して点検すれば、早期発見が可能になります。
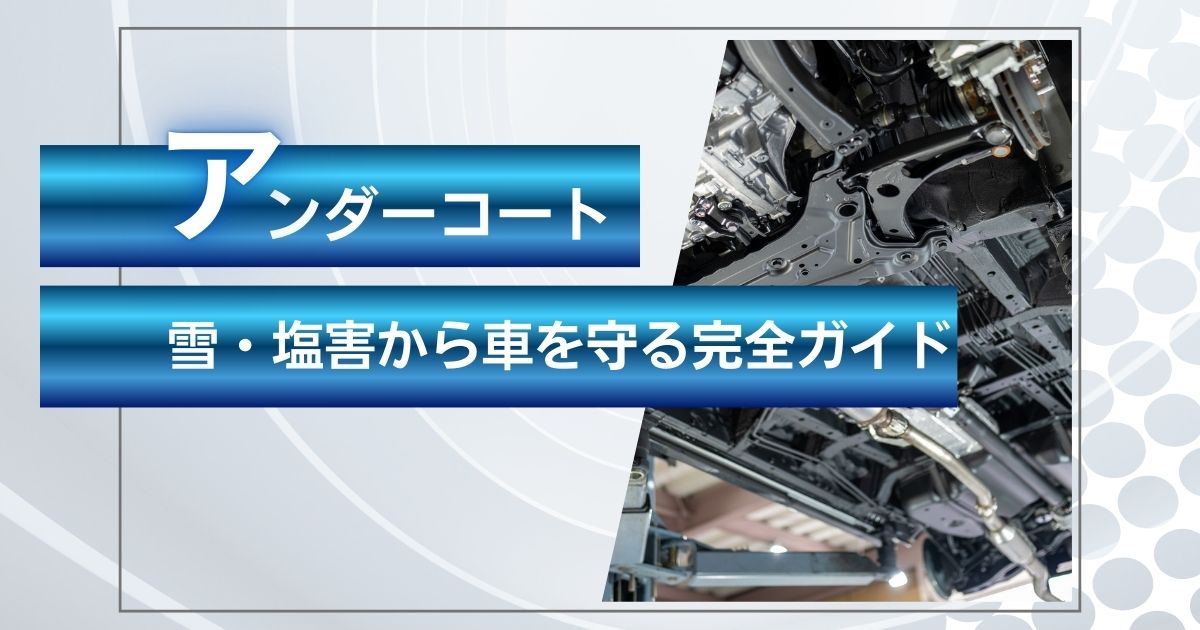
サビを放置するとどうなる?
サビは見た目の問題だけではなく、車の安全性や資産価値に直結する重大なトラブルへとつながります。放置すればするほど進行が早まり、修理も大掛かりになってしまうため、早めの対応が肝心です。
車検や安全性への影響
進行サビは、車検の検査基準にも関わります。特にフレームやサスペンションの取り付け部など構造部分の腐食は、強度不足と判断され、不合格になるケースがあります。
また、穴あきや亀裂がある状態で走行すると、部品の脱落や事故の危険性も。サビは単なる外観の劣化ではなく、命に関わるリスクになることを忘れてはいけません。
修理コストの増大
表面サビの段階であれば、研磨や部分補修で比較的安価に直せますが、進行サビや穴あきになると部品交換や溶接修理が必要になります。
例えば下回りフレームやパネルの交換は、10万円〜数十万円の修理費がかかる場合も珍しくありません。早期発見・早期対処が、費用を最小限に抑える最大のポイントです。
下取り価格の低下
サビは査定時に大きなマイナス評価となります。特に下回りのサビは目視検査で必ずチェックされるポイントです。
軽度でも減額され、進行している場合は大幅な査定ダウン、最悪の場合「買取不可」と判断されることも。日頃から防錆やメンテナンスをしておくことで、売却時の資産価値を守ることにつながります。
DIYでできるサビ除去方法(安全面の注意付き)
DIYでのサビ取りは、軽度の表面サビであれば十分に対応可能です。ただし、広範囲や構造部材の腐食は安全性のためプロ施工がおすすめです。ここでは軽度~中程度までのサビ除去手順を紹介します。
必要な道具とケミカル
- サンドペーパー(150番→320番→600番→1000番)
- スポンジブロック(サンドペーパーを巻き付けて均等に研磨するため)
- サビ取りクリーム(例:ソフト99 サビ取りクリーム)
- 錆転換剤(例:ホルツ サビチェンジャー)
- タッチペンやスプレー塗料(仕上げ用)
- 防錆スプレー
軽度のサビの除去手順
- サビ部分を洗浄・乾燥させる
- サビ取りクリームをクロスに取り、優しく擦る
- 5〜10分放置後、布で拭き取る(落ちない場合は時間を延長)
中程度のサビ(盛り上がり有)の除去手順
- サンドペーパーの粗目(150番)で表面のサビを落とす
- 中目(320番)→細目(600番)→極細(1000番)で面を整える
- サビ取りクリームで仕上げ
- 錆転換剤を塗布(進行抑制)
- タッチペンやスプレー塗装で保護
※サンドペーパーはスポンジに巻き付けて使用すると均一に削れます。
広範囲や液だれしやすい箇所の対応
- 広範囲 → 筆タイプの除去剤をたっぷり塗布し、放置後に拭き取り
- 垂直面(ドアエッジなど) → ペーストタイプを使用し、液だれを防止
DIYで対応できないケース
以下のような場合は、DIYではなくプロの修理が必要です。
- フレームやサスペンションなど構造部材に及ぶサビ
- 広範囲にわたる進行サビ
- サビの下に穴あきや内部腐食がある場合
- 溶接や部品交換が必要なケース
安全性に直結する部分は、無理せず専門店に相談することが、長く安心して車に乗るための近道です。
プロによるサビ除去と修理方法

DIYで対応できないサビや、安全性に関わる部位の腐食は、迷わずプロに依頼するのがベストです。専門店では、専用の機材・ケミカル・技術を駆使し、見えない部分まで確実に処理します。
専門機材とケミカルによる除去
プロ施工では、次のような工程と機材が使われます。
- 高圧洗浄機・スチーム洗浄機で汚れ・油分・塩分を徹底除去
- サンドブラストや電動研磨機でサビを効率的に削り落とす
- 残留サビには業務用の強力な錆転換剤を使用
- 耐久性の高い防錆塗料(ウレタン系・ゴム系など)を塗布し長期保護
こうした処理により、DIYでは難しい奥まった場所や構造部品の裏側までケアできます。
部品交換や溶接補修が必要なケース
サビが進行し、穴あきや強度低下が見られる場合は、部品交換や溶接補修が行われます。
- パネル交換:ドアやフェンダーなど、取り外し可能な外装パーツを新品または中古品に交換
- 溶接補修:フレームや床面など構造部を切り取り、新しい鉄板を溶接して補強
- 部分パネル形成:既存部品の一部をカットし、必要部分だけ鉄板成形して溶接
これらの作業は高度な技術を要し、DIYでは不可能です。
費用目安と作業期間
- 軽度のサビ除去・再塗装:1万〜3万円程度、半日〜1日
- 中度のサビ除去・防錆塗装:3万〜10万円程度、1日〜3日
- 部品交換や溶接補修を伴う重度修理:10万〜30万円以上、数日〜1週間以上
※車種やサビの範囲、部品入手の可否によって費用は大きく変動します。
サビの再発を防ぐ方法(簡易防錆)
せっかくサビを除去しても、そのままでは再発してしまう可能性があります。ここでは、自宅やガレージで手軽にできる簡易防錆対策をご紹介します。
DIYでできる簡易防錆スプレー
- 油膜系スプレー:浸透性が高く、ヒンジやボルトなど細部の防錆に効果的
- ワックス・樹脂系スプレー:表面に被膜を作り、水や塩分を遮断(ホイールや外装パネルに向く)
市販品で使いやすいのは、カー用品店やホームセンターで手に入る防錆ワックススプレーです。施工後は乾燥させてから走行してください。
部位別の防錆ケア
- 外装パネルの小傷 → タッチペンやスプレー塗装で保護
- メッキパーツのサビ → ソフト99「サビ取りクリーム」で除去後、防錆スプレー仕上げ
- 進行サビ箇所 → 研磨後にホルツ「サビチェンジャー」で錆転換+塗装
洗車後の水分除去と乾燥
水分はサビの最大の原因です。洗車後は以下を徹底しましょう。
- マイクロファイバークロスで全体を拭き上げ
- エアブローやブロワーでドア下・モール隙間・給油口などの水を飛ばす
- 冬季や雨天時は特に念入りに乾燥
定期的な下回りと外装のチェック
- 年1〜2回は下回り点検(タイヤ交換時がおすすめ)
- ホイールハウス内やボディの端部も要確認
- 早期発見・即処置がサビの拡大防止につながります
長期的な防錆を狙う場合は、アンダーコート施工が有効です。
外装の軽度サビはDIYでケアしつつ、広範囲や構造部の防錆はプロ施工を検討しましょう。
まとめ|サビは早期発見と予防がカギ
車のサビは見た目の劣化だけでなく、安全性や車の価値を大きく損なう要因です。
表面サビの段階ならDIYで比較的簡単に除去できますが、進行して構造部にまで及ぶと、修理費用も高額になり、車検にも通らないケースがあります。
この記事で紹介したように、
- サビの種類と発生原因を理解する
- 状態に合った除去方法を選ぶ
- 再発防止のための防錆処理を行う
この3つを押さえることで、愛車を長くきれいな状態に保つことができます。
DIYで難しい場合や広範囲のサビは、迷わずプロに依頼することが最善策です。
特に下回りや構造部の防錆は、アンダーコート施工が有効です。
早期発見・早期対処を心がけ、日頃の点検とケアで大切な愛車を守りましょう。